インラック株式会社
-未経験の高齢者も充実した教育訓練制度で戦力化-
- 70歳以上まで働ける企業
- 人事管理制度の改善
- 戦力化の工夫
- 能力開発制度の改善
- 上限年齢なしの継続雇用(基準あり)
- 技能伝承
- 新職場・職務の創出
- 研修制度の充実
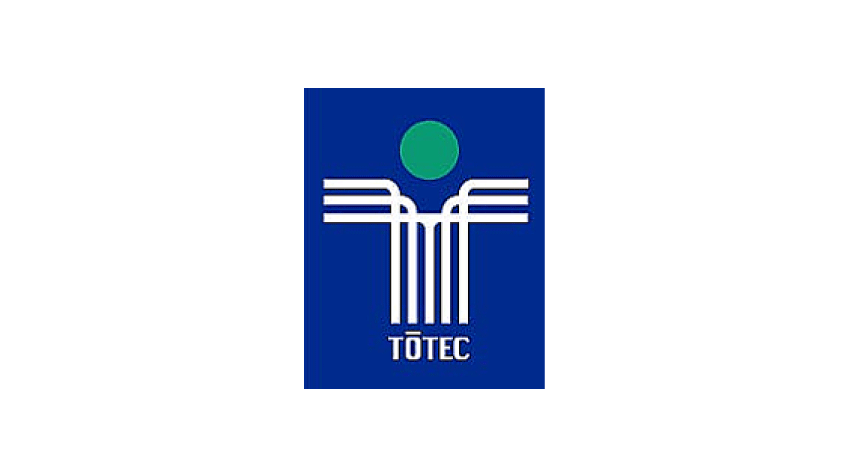
企業プロフィール
-
創業2008(平成20)年
-
本社所在地愛知県一宮市
-
業種その他の事業サービス業
-
事業所数4ヵ所
導入ポイント
- 高齢者であっても学ぶ意欲と謙虚さがあれば新規採用
- 未経験高齢者にも警備業法で定める新人研修の時間数を上回る研修を実施
- 管理職が頻繁に現場を訪れて高齢社員の要望と勤務環境を把握
-
従業員の状況従業員数 133人 / 平均年齢 58.0歳 / 60 歳以上の割合 50.4%(67人)
-
定年制度定年年齢 70歳
-
70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 上限なし 基準該当者
同社における関連情報
企業概要
インラック株式会社は2008(平成20)年創業、各種施設警備や店内保安業務、交通誘導警備やイベント警備、身辺警備等の警備業務、防犯機器販売・施工を行なっている。これからはあらゆる方面で危機管理業務が非常に重要になると考えた現社長が危機管理業務のプロフェッショナル集団として起業した。愛知県や岐阜県で事業展開し、本社と支社、営業所を擁し、社員の大半を占める警備業務従事者は、支社と営業所に所属している。本社の管理職、支社長や営業所長など管理部門の社員は比較的少なく、大半は現場で勤務する警備業務従事者であり、管理部門社員の多くは現場経験者から登用されている。
社員は133人(正社員104人、非正規社員29人)である。社員の年齢構成をみると60歳未満が66人、60歳代前半が25人同後半が25人、70歳以上が17人、全体の平均年齢は58歳である。

雇用制度改定の背景
■業務の実際
警備業では、警備を委託される現場は毎回多様である。一人勤務もあれば数人での勤務もある。短時間や短日数勤務もあれば長期にわたる現場もある。また、現場の約5割は警備員が直行直帰するが、現場スペースが限られて警備員が自家用車で通えなければ、営業所に皆が集合して車1台で出向くなどの対応となる。
歴史のある老舗の顧客は警備員として高齢者を、一方、若い会社は若手の警備員を望む傾向があるが、一般的にコミュニケーション能力の高い高齢警備員の需要は多い。また、同僚やいっしょに仕事をする者との間でも良好な関係が構築できなければ現場の安全は確保できず、高齢社員にも他者に対する丁寧な態度が求められる。
■経緯
2020(令和2)年、インラックは就業規則を改正し、定年を65歳から70歳へ延長した。従来から65歳定年以降も働き続けたいと考える高齢社員は多く、定年後の再雇用者も多かった。同社にとっても警備業務に熟達した高齢社員は65歳でも問題なく職務を遂行できること、警備業界は全般的に人手不足であり、同社が65歳定年のままでは、同社が長年かけて育成し、警備業務に関する知識や経験、技術を培ってきた高齢社員が70歳まで働ける同業他社に流出する恐れが強く、同社にとっては大きな損失となる。そこで同社は高齢社員がより長く働ける環境を整備したいと考えた。
人事管理制度の概要
■採用
インラックでは、警備業務従事者の大半をハローワーク経由で採用している。20歳代から70歳代まで幅広く応募があり、前職は建築や飲食など多彩である。同社は採用活動で高齢者の採用も積極的に行っている。面談や業務説明を通して本人の意欲を確認して採用する。同社が求める人材は「過信のない人」であり、警備業務経験者であっても初心を忘れた者ではなく、未経験者でも学ぶ気持ちを持つ人材を求めている。
応募者の大半は警備の仕事は未経験であり、「警備業はきついと聞くがやっていけるのか」と質問してくるなど不安を抱えている。同社では初心者でも警備のプロになれるように教育訓練制度を整備していること、他社よりも充実した福利厚生制度があることを説明しながら応募者の不安を取り除いている。未経験者であっても、同社の考え方や仕事の進め方を理解して身に付ければ問題はないばかりか、入社後立派に業務を遂行してくれるという。
■給与体系と人事評価
同社の給与体系は、基準内賃金(基本給と資格手当)と基準外賃金(各種手当)からなる。基本給は年功や年齢ではなく、業務経験や担当業務、実績で評価、決定される。国家資格や警備業関連資格を持つ者には資格手当が支給される。
同社の社員は各営業所に配属されて勤務し、営業所長が各人の仕事ぶりを見極めて評価する。日常の職務遂行だけではなく、随時行われる研修の成績や資格取得状況も評価の対象としている。年1回の査定により昇給する。評価内容は面談で各人に伝えられる。
社員のほとんどは警備業務に従事しており、単独もしくは少数で現場に派遣されて勤務している。上司である営業所の責任者は現場を回りながら各人の仕事ぶりを確認し、その仕事ぶりに対する顧客からの評価を聞く。顧客からは「安全確認がしっかり行われている」、「仕事ぶりが丁寧」、「通行人とのトラブルがない」などのコメントが寄せられる。顧客の評価が高い高齢社員は同じ顧客から依頼される次の警備業務にも指名されることが多い。これらの情報は査定に活かされている。
■継続雇用制度
70歳定年後も1年更新で年齢上限のない継続雇用制度(再雇用)が就業規則に明記されている。登用の条件は職務遂行に関する10段階評価で7以上と評価された者であるが、通常の勤務成績であれば継続雇用決定となる。継続雇用時の処遇は定年前と変わらず、評価結果によっては昇給もある。
同社の警備員の最高齢者はアルバイトの76歳、月8~10日の勤務となっている。定年後の継続雇用者の最高齢者は73歳である。継続雇用者となった高齢社員の一部はフルタイムで働いている。
高齢社員戦力化のための工夫
■若手社員への技能伝承
警備担当者が赴く現場は状況が毎回異なる。高齢社員はさまざまな現場での経験がある者が多く、注意すべき点や起こりうる事態などを把握しているだけではなく、突然起こる事態への対処力もある。加えて対人対応も丁寧であることから、顧客である企業や店舗、工事業者とのコミュニケーションも円滑になる。
インラックは高齢社員がこのような総合力を若手社員に伝えてくれることを期待している。そこで高齢社員と若手社員をペアにして現場に派遣し、共同して業務にあたらせている。高齢社員は自身の役割や任務を認識し、教え手としての自覚も高まり、仕事にやりがいを感じ、意欲も高まっているという。
■教育訓練の充実
同社では社員の教育訓練に力を入れている。警備業法改正により、警備業務に従事するための新人研修で求められる時間数は30時間から20時間に短縮されたが、同社では現在も30時間をかけている。この30時間中、15時間が基本教育(警備業務の違いにかかわらず行う共通の教育)、残りの15時間は研修後に配属される担当業務の違いを反映した内容となっており、現場実習も含まれる。個人差もあって研修の内容に追い付くのに時間のかかる者もいるが、同社では30時間を超えて教育することもある。また、研修減免可能な国家資格保有者に対しても改めて研修を受講させている。
同社には講師として研修を担当できる社員が10人以上いる。講師は会社の用意したテキストに加えて自分で作成した教材も使用して研修を進めている。

■資格取得の奨励
同社では社員向け研修を年2回行なう他、各人の業務遂行を高度化かつ円滑にするために各種資格取得を奨励し、取得に必要な費用も援助している。
高齢社員の中には年をとってからの資格取得のための勉強を躊躇する者もいる。「資格取得のためにこれから勉強するのは大変」、「勉強しても資格は取れないのでは」とあきらめようとする高齢社員に対しても会社は粘り強く取得を促している。
資格を取得できれば給与も上がるため、高齢社員にとって得るものは大きい。また、同僚に資格取得者が出れば「自分もやってみようか」との波及効果も期待でき、全社的なレベルアップ・底上げが期待できるという。
■SNSを活用した連絡体制構築
各地の現場で働いている社員の状況を随時把握するため、同社ではSNSを活用した連絡方法を確立した。これにより会社から複数スタッフへの多様な連絡、社員から会社への緊急の連絡や報告、相談が円滑・簡略に行えるようになった。
■負担の軽い職務の開発
高齢になって現場でのフルタイム勤務が負担となった場合でも、現場での短時間勤務や現場巡回などのサポート業務、また、営業所内での業務に従事することで働き続けることは可能である。
■大学との共同研究
同社は「生涯現役」実現に向け、社員の労働環境改善に向けた取り組みを強化している。一例として、岐阜大学との共同研究がある。この共同研究では、片側交互通行時の誘導作業について、ベテラン警備員と経験の浅い警備員の行動を撮影してAIが分析、車両を停める適切なタイミングをノウハウとして蓄積し、誘導作業のサービス品質向上につなげている。誘導にあたる警備員の現場での心理的負担が軽減され、より注意すべき点に警備員が注力できるようになった。同社における機械化・自動化は労働力の代替ではなく、働く者がより高度な仕事をするため、働きやすくするための手段である。
健康管理・安全衛生
■健康診断結果のフォローアップ
インラックは社員の定期検診の結果を重視し、「要検査」となった者は必ず再検査に行かせている。支社長や営業所長は日常から高齢社員を含め社員への声掛けに努めており、高齢社員個々人の変化を見逃さず、負担の重い現場から比較的軽い現場への変更など業務の調整を行う。
■屋外作業対策の充実
気象条件がさまざまな屋外作業に配慮し、事故防止のためのパトロールを随時行っている。夏期は熱中症対策として空調服を導入した。また、保冷剤が4個入る冷却ベストを試験的に貸与したところ好評であり、社員全員分を確保している。加えて熱中症重点巡回、塩飴やサプリメント、スポーツドリンクの配付も行っている。冬期はヒーター付きベストを貸与している。
■新型コロナ感染予防対策の充実
ここ数年の新型コロナウイルス感染予防対策として検査キットを常備し、また、感染した社員が療養できるよう社宅の部屋を確保したが、幸いに現在まで感染者は出ておらず、使用することなく推移している。
■安全衛生に関わる研修の開催
同社では外部講師も招いた安全衛生研修を随時行っている。研修では受講者にアンケート調査も実施し、改善提案も集め、会社と社員で情報共有のうえ、改善に努めている。
制度改定の効果と今後の課題
■定年廃止を視野に入れた将来構想
仕事を続けるには年齢よりも体力や健康面が決め手となるため、年齢で一括りにすることは問題が多いとインラックでは考えていた。高齢社員の就労に対する姿勢、経験豊富な知識が同社に対する高い貢献につながっていることから、安心して働ける環境を充実させるため、将来的には定年廃止を視野に環境整備に努めていくとしている。
同社では、高齢者雇用の観点からも新しい事業展開を構想している。体力的な限界から警備業務が難しくなった高齢社員の生活拠点の提供を目的として高齢者施設を開設し、老後の生活の不安なく生活できるようにすることを検討している。
