コマニー株式会社
-65歳以降は年齢上限のない新たな働き方の新制度を導入-
- 70歳以上まで働ける企業
- 人事管理制度の改善
- 賃金評価制度の改善
- 戦力化の工夫
- 上限なしの継続雇用(基準あり)
- 多様な勤務形態
- 新職場・職務の創出
- 研修制度の充実
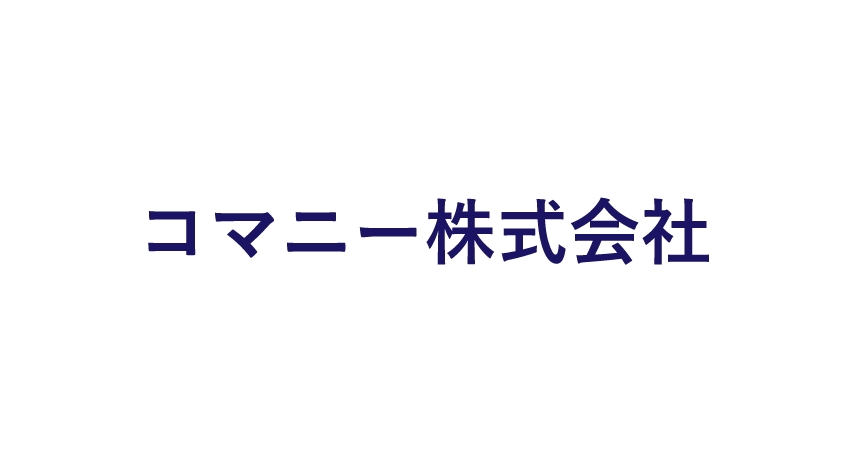
企業プロフィール
-
創業1961(昭和36)年
-
本社所在地石川県小松市
-
業種その他の製造業
-
事業所数27ヵ所
導入ポイント
- 60歳定年後は65歳まで「嘱託社員」、65歳以降は上限年齢なしの「契約社員」
- 高齢社員が講師の「施工アカデミー」が若手社員の技術力向上に貢献
- 女性がQCサークル活動で改善した工具や設備が高齢社員の負担を軽減
-
従業員の状況従業員数 1,257人 / 平均年齢 42.2歳 / 60 歳以上の割合 8.8%(110人)
-
定年制度定年年齢 60歳 / 役職定年 なし
-
70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 希望者全員 。65歳以降は一定の条件の 下、上限年齢なく再雇用
同社における関連情報
企業概要
コマニー株式会社は、1961(昭和36)年創業のパーティション(間仕切り)専業メーカーである。「小松キャビネット株式会社」として創業した当時はキャビネットやロッカーを製造販売していたが、自社技術や設備、販売体制を効果的に活かせる製品としてスクリーン(衝立)に着目、その後、パーティション事業に特化、1970(昭和45)年には「株式会社小松パーティション工業」に、そして1984(昭和59)年、現在の社名に変更した。パーティション製造販売では国内有数の企業である。

石川県小松市に本社、工場は本社の敷地内に併設の工場と埼玉工場、また、全国27ヵ所に営業所を擁する。部門は営業、工務、開発、設計、企画管理、施工、製造等からなる。社員数は1,257人(うち非正規社員は150人)、年齢構成は60歳未満1,147人、60歳代前半76人、同後半29人、70歳以上5人であり、60歳以上の比率は8.8%、平均年齢は42.2歳である。
パーティションは用途に応じて空間を分けるための設備であり、オフィスや工場、学校や病院、駅や空港などさまざまで場所で使われる。その用途はトイレを始め、オフィスの会議室や個室タイプの事務スペース、工場のクリーンルームなど多様である。製品は外板となる表面材の内側に裏打材が接着され、両面の外板は枠材を挟んで厚みを調整、枠材の内部は充?材である紙製のペーパーコアや石膏ボードで満たされる。また、裏打材と枠材がなく、充?材を表面材で挟んだ3層構造のものもある。工場で生産されるパーティションは納入される現場ごとに大きさや構造が異なる。納期の制約があるなかで、ベテラン作業者が外板と枠材の間に収まるように切断したペーパーコアを挟み込み、パーティションを組み立てる。パーティションは耐久性や耐衝撃性、清潔性や防音性、メンテナンスのしやすさが求められるだけではなく、あらゆる人々が使いやすい機能、空間全体と調和したデザインが要求される。同社は新たに生まれるニーズに対応したパーティション商品を開発、「間仕切りメーカーから間づくりをする企業へ」変身を続けている。

雇用制度改定の背景
コマニーの経営理念は「全従業員の物心両面の幸福」であり、社員一人ひとりの身体的・精神的・社会的なウェルビーイング(幸福・健康)の実現を目指している。同社の定年年齢は60歳である。定年後の継続雇用について、これまでは65歳まで嘱託社員として再雇用される制度が設けられていた。
2021(令和3)年4月、同社は制度を改定、65歳以降の新たな働き方の新制度を導入、上限年齢を撤廃した。その背景には厚生年金受給開始年齢の段階的引き上げや、70歳まで働ける会の確保を企業の努力義務とする高年齢者雇用安定法改正案の発表があった。この機を捉え、同社のトップは「健康、能力があればいつまでも働ける会社にしよう」と社員に発信、65歳以降もいつまでも働ける会社が実現した。「人生100年時代といわれる中、年齢にとらわれずに可能な限り仕事で長く活躍できる環境を築くことが、従業員にとってより実りあるライフプランを描けることにつながる」と確信した同社は、65歳以降の新たな働き方の制度として「シニア社員等雇用制度」を導入した。
人事管理制度の概要
■採用
コマニーの社員の年齢構成は、若手と高年層が多く、中間の年齢層が比較的少ない。そのため新卒採用と並んで中途採用も強化している。中途採用では設計管理や施工管理、営業、工務(工事管理)の経験者を対象に「キャリア採用」に力を入れている。
■処遇
同社の賃金体系は基本給と諸手当からなる。基本給は年功給をベースに人事考課による評価を反映させている。営業社員の場合は成果給部分を含めている。年1回昇給する。賞与は評価結果を反映して決定する。退職金は60歳定年時に支給している。
■65歳までの嘱託社員制度
同社では60歳定年後の社員は希望者全員65歳まで「嘱託社員」として再雇用する。職務はそれまでと変わらない。なお、業務上の必要から引き続き役職に留まる場合がある。給与は定年前から若干低下する。フルタイム勤務が原則であるが、個人の事情に応じて短時間勤務も認めている。
■65歳以降の「シニア社員等雇用制度」
シニア社員等雇用制度は、継続雇用制度と業務委託契約制度(※)からなる。継続雇用制度では65歳到達時に本人が希望し、健康状態、本人の技能・能力、本人の評価を参考にして会社が認めた場合、「契約社員」として1年更新で上限年齢なく再雇用される。契約社員は時給ベースでの処遇となり、フルタイムだけではなく短時間勤務も可能である。職務内容はそれまでと変わらず、65歳までの嘱託社員(定年再雇用)の賃金がベースとなる。
業務委託契約制度は、同社が職制や必要とされる資格・スキルを持つ社員と業務委託契約を結ぶ。設計などの個人スキルで自由な働き方をベースに同社の業務をすることができる。過去、現場監督経験者が独立を希望して退職したことがり、専門知識や資格を持つ人材の社内活用策として制度化された。これにより、独立したい社員の願いを叶え、同社は優秀な人材を活用できる。現在、業務委託契約制度の対象者はいないが、これからの活用が期待されている。
高齢社員戦力化のための工夫
■施工アカデミー講師による人材育成
施工部門の社員は全国各地の営業所に配属され、現場でパーティションを設置する。社員は基礎的な技術や技能だけではなく、毎回異なる現場で的確、迅速に作業を行うための応用力も必要とされる。コマニーでは従来から施工社員向けの教育訓練を行ってきたが、いっそうの充実のため、2020(令和2)年から本社工場内に「施工アカデミー」を設立、若手社員の教育に力を入れている。対話を重視して教えるアカデミーで訓練を受けた若手社員の施工技術は向上し、自信をつけた社員が各地で活躍している。
アカデミーの講師には60歳を超えた社員が就任している。テキストは電子化し、タブレットで教育しており、フルタイム勤務の講師もタブレットを用いて生徒を指導している。講師職の後継者も育成が進んでおり、現講師が勤めた後、現在50歳代の社員が、60歳以降の業務として引き継ぐ予定である。

■作業設備・工具の改善
同社の製品が多様な人々を対象としていることから、会社ではダイバーシティ &インクルージョン活動を推進し、社員である高齢者や女性、障害者一人ひとりの個性や属性の違いを尊重し、相互に緊密なコミュニケーションを図って多様性を受け入れ、活かすことのできる組織風土の醸成を進めてきた。この取り組みが高齢社員の働きやすさを実現している。
同社ではQC(品質管理)サークル活動が盛んであり、製造部門の女性社員で構成したサークルは女性の視点から働きやすい職場作りを目指し、部材を持ち上げずにスライドさせて移動できる作業台の改善や重い工具の軽量化を実現した。この成果が製造部門の高齢社員の体力負担軽減につながっている。
■若手社員と高齢社員の相互理解促進
同社では若手社員と高齢社員が共に参加する研修を実施している。研修では仕事に対する考え方について両者それぞれが発表する。お互いの発表を題材に議論するなかで世代を超えた相互理解が深まっている。
■ライフプランセミナーの実施
同社では特に50歳以降の社員に向けてライフプランセミナーを実施し、健康面や生活面の情報を提供する。また、面談では60歳以降の働き方について職務や勤務時間などの希望を聞いている。会社から社員に対しては、定年後も同じ職場で働きながら、特に上司のサポートや若手育成に励んでもらいたいと伝えている。一方、現場で体力も使う施工の職務は高齢社員の負担が大きくなる場合があり、勤務時間短縮や職務変更も検討される。
健康管理・安全衛生
■作業環境の改善
コマニーの本社工場内の建屋内部は広く、夏場は空調を行っても暑くなる。そこで大型シーリングファン2基を導入した。この設備は小さな力で広範囲に大きな風を発生させることができるため作業者の体感温度を下げ、熱中症リスクを低減できる。冬場の暖房効率も向上し、作業環境改善とコスト低減、地球環境配慮を実現している。
■在宅勤務制度の充実
柔軟な働き方を目指し、同社では従来から設計部門を中心に在宅勤務を取り入れていた。新型コロナウイルス感染拡大後は在宅勤務をさらに推進している。
■健康管理体制の充実
高齢社員の中には体力や身体機能低下が起きることも予想され、健康問題や安全対策も課題となる。同社では健康診断結果を注視し、健康管理にいっそう努めている。
制度改定の効果と今後の課題
■「働き続けたい意思」の掘り起こし
コマニーが65歳以降も働ける制度を設けたことで、社員の意識も変化している。希望すれば誰でも年齢制限なく働けることから、いつまでも同社で働きたいと考えていた社員は実際に意思表明して働くようになった。また、「制度があるなら働こう」という者も現われ、「働きたい」という社員の潜在的ニーズを掘り起こすことが可能となった。
■60歳以降の働き方を選べる制度
同社では60歳以降の働き方をコース化し、60歳定年後も同社で働く社員が勤務内容や勤務形態、給与を自身で選べる制度を検討中である。現在、勤務形態については個別に決定しているが、より分かりやすく体系的な制度に改め、社員主体のキャリア設計の実現を目指している。
■評価制度の確立
年齢制限なく働ける社員の意欲をいっそう高めるため、同社では高齢社員の評価制度のあり方を検討している。65歳以降の契約社員を対象に評価を行い、賞与に反映させる計画である。
■年齢構成バランスの維持
現在、同社の60歳定年到達者は年間10人から20人程度で推移している。一方、これからはその数が倍増すると予想される。65歳以降も働き続ける社員の増加は年齢構成に影響するが、新卒採用によって年齢構成のバランスをとることとしている。
■活き活き働ける職場、環境づくり
65歳以降いつまでも働ける制度は社員に安心感を与え、歓迎すべきものであるが、同社にとっては人件費負担が増加する。しかし、同社は負担を上回る効果を期待し、その実現に自信を持っている。一人ひとりの社員が65歳以降も自分に合った働き方を考え実現し、これまで培ってきた知見や経験を業務や後進育成に活かし、健康で意欲を持って元気に活躍し続けることができる職場、環境づくりを推進し、全社員がその能力を最大限に発揮し、活き活きと誇りを持って働き続けることができる企業を目指している。
