社会福祉法人佐賀西部コロニー
-「互譲互助」の経営理念で高齢職員も障害者も活き活き働ける場-
- 70歳以上まで働ける企業
- 人事管理制度の改善
- 賃金評価制度の改善
- 戦力化の工夫
- 賃金・評価制度改定
- 多様な勤務形態
- 新職場・職務の創出
- 作業環境改善
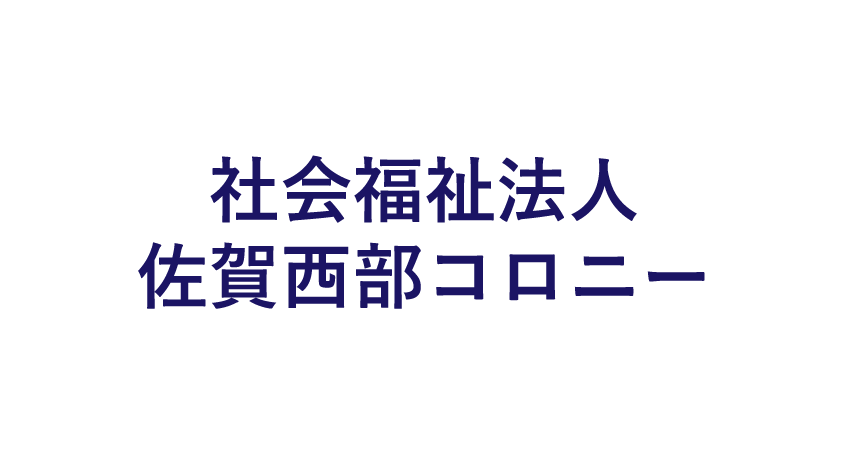
企業プロフィール
-
創業1984(昭和59)年
-
本社所在地佐賀県藤津郡
-
業種社会保険・社会福祉・介護事業
-
事業所数4ヵ所
導入ポイント
- 障害者が活き活き働ける場つくりに経験豊かな高齢職員が貢献
- 高齢職員ならではの事情に合わせ変形労働時間制や時間単位の有給休暇制度を導入
- 継続雇用の高齢職員も貢献度に応じて昇給
-
従業員の状況従業員数 72人 / 平均年齢 55.0歳 / 60 歳以上の割合 44.4%(32人)
-
定年制度定年年齢 65歳 / 役職定年 なし
-
70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 73歳 希望者全員
同社における関連情報
法人概要
社会福祉法人佐賀西部コロニーは1984(昭和59)年設立、「互譲互助」を経営理念に、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所(就労継続支援B型)、グループホームを運営する。
職員数は72人、うち正規職員31人、非正規職員41人(嘱託職員40人、パート1人)、職員の年齢構成は60歳未満が40人、60歳代前半が19人、同後半が8人、70歳以上5人、全体の平均年齢は55歳である。職員の職務は多岐にわたり、管理者、サービス管理責任者、生活支援員、職業指導員、栄養士、世話人、目標達成指導員等から構成される。同法人の特徴は法人設立時から行なっている「循環型リサイクル事業」にある。地域の森林資源(間伐材)を活かして木工品を製作、その際に生じる端材を砕いて固めて菌床にしキノコを栽培、次に菌床として使えなくなった廃材でカブトムシを養殖し、養殖使用後の廃材は園芸肥料となる。資源はすべて法人内でリサイクルできる。キノコ栽培やカブトムシ養殖の作業には障害者が携わり、販売したキノコやカブトムシの収入でB型事業所の工賃を全国平均の2倍に引き上げている。
また、「地域元気営農事業」として地域の高齢農家の遊休みかん園を取得して農業にも参入、同法人代表が考案した「海水農法」でみかんを栽培する他、高齢農家に海水農法によるさつま芋栽培を委託して買取り、販売している。農業作業にも同法人を利用する障害者が参加し、さつまいもの栽培や海水散布、出荷作業に従事している。

雇用制度改定の背景
■経緯
2020(令和2)年、佐賀西部コロニーは定年をそれまでの60歳から65歳へ延長した。同時に定年後の継続雇用については希望者全員を1年更新で73歳までとし、就業規則に明文化した。従来から定年退職者が定年後もパート職員として働くことが多く、高齢職員の多くは継続雇用を希望していた。一方、法人経営の観点からも若年者採用が難しい地域特性や業務経験豊かな高齢職員の活用が欠かせない点から、定年が延長された。多くの職員から「安心して働くことができる」と好評である。現在、定年後の継続雇用者は5人いる。
■制度改定に向けた課題とその対応
同法人では65歳定年実施を契機に高齢者雇用をより効果的に推進するため、従来の制度を見直し、高齢職員が働きやすい職場環境整備に取り組んでいる。高齢職員活用方針は「法人理念の実現のため、高齢職員がこれまで培った経験・ノウハウを最大限発揮できるように、制度や職場環境等を整え、年齢にかかわりなく働き続けられる法人を目指す」である。
人事管理制度の概要
■新規採用と定年後継続雇用
佐賀西部コロニーに採用される者はまず嘱託職員として入職する。公平性の観点から正規職員と嘱託職員の業務明確化を通して両者の賃金等の格差は改善されている。嘱託職員はその後、登用試験を経て正規職員となる。一般職以上の管理階層は責任者、課長、部長、管理者となっている。定年後は嘱託職員となるが「リーダー嘱託職員」の呼称を持ち、正規採用前の嘱託職員と区別される。
■人材育成方針
同法人の教育訓練は、①新入職員教育、②安全衛生教育、③外部研修、④資格取得、⑤自己啓発、からなる。同法人の以前の人材育成方針ではまず個人が目標を立て、それを法人が支援していた。個人主導で進められるので意欲の高い個人には動機付けとなるが、実際に取り組むテーマや進め方には個人任せの部分もあった。
2018(平成30)年から法人が求める人材像を改めて検討、育成に必要な内外の研修を組み合わせた育成カリキュラムの運用を開始した。その後、2020(令和2)年に教育訓練規程として制度化、法人全体で職員の人材育成に取り組む環境を整えた。
■キャリア形成
同法人では正規職員と非正規職員に毎年「キャリアパス要件」の表を配付する。このキャリアパス要件表には各職員が勤続年数や職責に応じてこれから進むべきキャリアパスについて、今後求められる役割、期待される能力(指導能力、危機管理能力、相談援助技術、人材育成能力、課題解決・業務改善能力、マーケティング能力、リーダーシップ能力、組織運営管理能力、経営能力)、権限や職務、昇進の目安となる年数等を明示し、加えてその実現のために必要となる教育明らかにしている。職員はこれから仕事をする上で何が必要となるのか、何を身に付けるべきかが分かる。キャリアパス要件表にはリーダー嘱託職員も位置づけられており、果たすべき役割が明示されている。
■目標管理制度
同法人の正規職員は毎年、「目標設定シート」に目標と達成スケジュールを書き込む。目標は目標項目(何を)、達成基準(どの程度)、期限(いつまでに)について、また達成スケジュールは具体的方法(どのように)を記載する。年度に管理職との面談で達成度を確認し、これをもとに新年度目標を設定する。目標達成には職場の同僚である高齢職員との協力も欠かせない。目標設定シートを通して若手職員や中堅職員と高齢職員のチームワークも向上しているという。
なお、同法人では各職員のこれまでのキャリアや受講してきた内外の教育訓練メニューを個人シートにまとめてデータ化している。管理職は各職員の個人シートを参考に次に提供すべき教育訓練メニューを検討できる。
■処遇
同法人の正規職員の給与は基本給と諸手当からなる。基本給は年齢と職務が反映される。年齢給部分は55歳まで昇給する。職務給部分は担当職務の業務や役割、責任を考慮して決定される。従来は職務の負荷がそれほど給与に反映されていなかったが、他の法人の賃金表を参考に、各職務の分析を行なって決定するようになった。諸手当には管理職・責任者手当、資格手当(社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、正看護師、調理師、理学療法士等国家資格を持つ者が対象)等がある。
賞与は年2回支給され、期末手当と職能手当からなる。前者はすべての職員に対して一律の支給率であるが、後者は人事考課の結果が反映される。退職金は独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済事業から支給される。
定年後のリーダー嘱託職員の給与水準は正規職員と異なるが、高齢期も意欲を持って働けるよう少額ではあるものの70歳まで昇給する。賞与も正規職員と同じく期末手当と職能手当が支給され、職能手当は人事考課が反映される。
■人事考課
同法人の人事考課は年2回支給される賞与の職能手当部分に反映される。各職員は年度初めに理事長から年度にあたって取り組むべき課題が示される。その課題の達成状況を事業所長が第1次評価、続いて全事業所長が合同で第2次評価して4ランクからなる最終評価を決定、平均賃金に業務評価率を乗じることで支給額が決定される。評価結果は賞与支給の際に事業所長コメントとして賞与明細に添付され、本人に手渡される。この方式は定年後も働くリーダー嘱託職員も同様である。
高齢職員戦力化のための工夫
■高齢職員の役割明確化
佐賀西部コロニーでは高齢職員の主要な役割を後継者育成と職場改善と位置づけている。定年退職して継続雇用者となる高齢職員に対し、法人は管理職との面談の場を設定して高齢職員に期待することを伝え、自覚を高めている。高齢職員は各部門にもれなく配属され任務に当たっている。高齢職員の持つスキルとして長年にわたって作業してきた生産や栽培の知識がある。これらは経験や勘も含めてマニュアル化しにくいものも多い。高齢職員は単に製造技術や
栽培技術だけではなく、ともに作業する障害者の動機付けや安全を考慮した作業手順や注意点を後継者である若手中堅職員に効果的に伝える役割が求められている。一方、これまでの管理職としての経験も年下の管理職に伝えながら管理業務を補佐する役割や、職員の要望を感じ取って現管理職に伝える調整役も期待されている。
■肉体的負担の軽減
各職場でも工夫を進めている。収穫物を載せるリヤカーの取っ手を半分切ってまたがずに使えるようにし、荷台に載せるコンテナが3個収まるように荷台サイズも改良した。これにより運搬作業が安全で楽になった。この改良は高齢職員が行なっている。
さつま芋を洗う作業では剥がれやすい芋の皮を傷めることなく丁寧に洗う作業が注意力を要し、かつ手洗いのために手の荒れと腰痛が生じがちであったが、この作業を自動洗浄機の自前開発で機械化し、作業者の負担軽減と生産効率向上を実現した。工芸部門の作業場にあった段差を木工部門が解消して転倒事故を防止、高齢職員も多く早朝勤務となる調理部門では休憩室を改装して疲労回復につなげている。

■変形労働時間制度の導入
同法人では定年後の嘱託職員も含めてフルタイム勤務が基本である。業務の性格から土日勤務も必要となるが、4週間単位の変形労働時間制度も採用しており、各施設では特定の曜日や時間帯の担当が同じ職員に集中しないようにシフトを工夫している。また、有給休暇は40時間を限度に時間単位での取得が可能であり、高齢職員からは孫の送り迎えや自身の通院に利用できるため好評である。
健康管理・安全衛生
佐賀西部コロニーでは高齢職員が障害者を指導しての農作業など屋外での肉体労働も多く、健康管理や安全衛生の取り組みが欠かせない。安全衛生では各事業所責任者を委員長にリスクマネジメント委員会を月1回開催し、ヒヤリハット事例や実際に発生した事故を検証、再発防止に努めている。
健康管理では定期健康診断結果に基づく二次検診受診を指導し、結果を把握している。高齢職員のなかには白内障など手術が必要となって仕事に制限が出る場合もあり、十分な治療を経ての職場復帰サポートを行なっている。
制度改定の効果と今後の課題
定年延長は長い期間働きたいと考えていた高齢職員から評価されている。また、高齢職員の役割を後継者育成と職場改善中心と明確化したことで、高齢職員が日々の仕事で目指すべき方向も定まった。若手職員の採用も円滑になってきた現在、彼らを将来の中心戦力とするための技能伝承が喫緊の課題となっており、後継者育成に励む高齢職員に負担の掛からない働きやすい環境を充実させることが佐賀西部コロニーの課題となっている。
