昭和化工株式会社
-定年延長2年前から従業員向け説明会を開催、事情や要望を把握-
- 70歳以上まで働ける企業
- 人事管理制度の改善
- 賃金評価制度の改善
- 能力開発制度の改善
- コンテスト入賞企業
- 70歳定年
- トップ主導の定年延長
- 技能・技術のマニュアル化
- 研修制度の充実

企業プロフィール
-
創業大正7年(1918年)
-
本社所在地大阪府吹田市
-
業種化学工業
-
事業所数2か所
導入ポイント
- 改定の契機:「社員が長く安心して働ける環境を」と考えた経営者のリーダーシップ
- 総人件費上昇よりも若手人材育成にも効果ありと判断し定年延長を決断
- 高齢者、若年層一丸となってマニュアルを見直し
- 70歳まで働く場合に不可欠となるPCスキル習得のため従業員を外部講習に派遣
- 改定の効果:高齢者を含め全従業員がITスキルを獲得、高齢者による若手育成も充実
-
従業員の状況従業員数 150人 / 平均年齢 44.4歳 / 60 歳以上の割合 17%(26人) 60~64歳 17人/65~69歳 8人 /70歳~ 1人
-
定年制度定年年齢 70歳 / 役職定年 なし
-
70歳以上継続雇用制制度の有無 該当せず / 内容 70歳定年
同社における関連情報
企業概要
昭和化工株式会社は1918(大正7)年創業、酒石酸など有機酸や無機薬品、機能性材料を製造する化学メーカーである。製品は食品添加物や医薬用原料として食品メーカーや製薬企業に、また電子関連部材の洗浄剤、各種製造設備の洗浄剤等の工業薬品として多方面の製造業に供給される。営業、技術、管理、人財、経営会議直下の課・係の各部門からなる。2023(令和5)年6月現在の従業員は167名、うち60歳未満147名、60歳代前半12名、60歳代後半7名、70歳以上1名、60歳以上者の比率は12.0%、平均年齢は43.4歳である。

雇用制度改定の背景
■社長のリーダーシップで定年延長を決定
定年は70歳、2018(平成30)年に60歳から70歳へ10歳引き上げている。70歳への定年年齢引き上げをはじめとした高齢者雇用の取り組みは厚生労働省大阪労働局と一般社団法人大阪府雇用開発協会から「高年齢者雇用優良事業所表彰」を受賞している。70歳定年導入後、現在の正社員の最高齢者は67歳、フルタイム勤務で製造工程の作業を担当し、原料仕込みや工程管理、製品の取り出しに従事している。
定年延長は社長のリーダーシップで進められた。経営者として将来的な労働力不足への対応を考えた時、すでに同社で働いており、かつ、高齢期になってもそれまでと遜色なく仕事を進めている従業員の存在は大きかった。「この会社に入ってくれた社員との縁をずっと大事にしていきたい」と社長は考えた。
定年延長は総人件費が上昇し、経営に大きく影響する。 一方、ベテランが今までより長く在籍することで労働力確保につながるだけではなく、若手への指導にあたれる期間も長くなり、人材育成を通した企業力強化に貢献できる。コストよりも会社が得られるメリットの方が大きいと考え、社長は70歳への定年延長を決断した。
■定年延長にともなう制度改定
70歳への定年延長を決定した同社はその実現に向け、社内制度の改定に着手した。総人件費上昇と会社の長期的成長を両立させるため賃金制度を見直し、60歳以降の賃金カーブを緩やかに低下させた。もっとも60歳定年時でも再雇用時の基本給を低下させており、制度改正後の賃金水準は以前より上昇している。
■定年延長実施2年前から説明会を開催
従業員代表と労働組合に対しての説明、従業員全体に対する説明会を定年延長実施の2年前から始めた。会社からは70歳定年を決定した理由や背景、その実現にあたって従業員に期待する役割を説明した。説明会では従業員の意見も聴取した。「長く働けるのが分かって安心した」と評価する意見もあれば、「体力的限界で70歳まで勤められるか分からない」との不安も聞かれた。定年延長の実施に際してはこれらの意見も考慮した制度設計となっている。
■複数の選択肢を用意
定年延長前は60歳定年後の再雇用制度(シニアスタッフ制度)が行なわれており、その対象者の処遇も解決すべき課題となった。同社は70歳定年実施後5年間に限り、旧定年年齢である60歳から再雇用者となれる選択を残した。この間は従来の再雇用制度(シニアスタッフ制度)と70歳定年制が同時並行となり、どちらかを選択可能とした。加えて旧定年後に再雇用となった者でも正社員に復帰可能とした。
人事管理制度の概要
■採用
毎年正社員・パート社員20名程度を採用している。新卒採用では高卒大卒を、中途採用では高齢者採用も積極的に行なっており、他社を定年退職後に採用された数名が在籍、安全衛生や管理部門、製造部門など様々な部門で配属されている。他社から採用した高齢者が語る経験や提案は従業員の意識改善のきっかけとなっている。
■教育訓練制度
教育訓練は新入社員研修から始まり、役職者研修や安全教育が行なわれている。また、試用期間中は製造部門で採用された人材は施設・設備保全部門で研修を行う。
施設・設備保全部門での業務経験によって製造工程時の異常が分かり、設備メンテナンスが出来る人材が養成される。
同社では高齢者にも若手と変わらない教育機会を与えており、資格取得に向けた会社の支援は高齢者も対象である。Eラーニング(一般常識、メンタルヘルス、女性活躍、決算書の読み方等)も実施している。
■賃金制度と評価制度
賃金は基本給(年齢給)、家族手当、役職手当、その他からなる。従業員は職能資格制度で格付けされている。能力評価で人事考課を行ない、所属長の一次評価と経営層の最終評価を経て、基本給に反映される。年齢給の昇給は60歳までとなる。 退職金は確定拠出型である。
■継続雇用制度
前述のように60歳定年時は定年後65歳まで希望者全員を再雇用する制度が存在した。人事考課も行なわれ、賞与も支給されていた。70歳定年制定後5年間はこの制度が存続したが、2023(令和5)年3月末に廃止されている。
高齢従業員戦力化のための工夫
■目に見えていない作業をマニュアルに
同社は各部門の業務マニュアル充実に努めている。製造部門は製品標準書を常備、製造工程で必要となる技術や技能を詳細にマニュアル化している。 従来からマニュアルは存在していたが、作業者によって品質に差が出ることがあった。マニュアルの記述に曖昧さが残っていたことが原因であった。ベテランから新人まで互いが自身の作業を振り返り、マニュアルと照らし合わせる。何の違いが品質に差を生むのかを明確にするため、感覚ではなく、文字に起こし、関係者で共有した。
その結果、目に見えない作業を可視化でき、作業者による品質のバラつき軽減に繋がった。
技術や技能を駆使して作業するベテランと経験の浅い若手が意見交換できる貴重な機会となっている。
■職場会でコミュニケーション促進
良くないことほど共有すべきという会社方針から毎朝、全従業員が当日の連絡事項以外にも前日発生した課題、計画変更などを共有している。その他、過去、社内で発生した課題は「風化させない」事項として共有化されており、それらの理解を深めるにはベテランの力が必要となる。各部門の繋がりや今の制度が始まった背景を理解することは会社の基礎を知るきっかけとなり、業務改善に取り組む際も1つの部門だけではなく、 会社全体を考えた取り組みに繋がっている。
また全従業員が週に1度、会社に報告書を提出している。中には部門単位での報告もあり、所属する従業員全員が会社からの指示事項、部門内の課題について話合い、報告している。高齢者から若手まで同じ業務に就く者が活発に意見交換をする場となっており、職場会以外にも深いコミュニケーションが取れる場として利用されている。
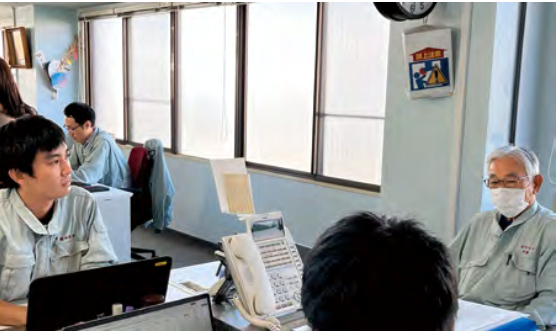
■全社でスキルの底上げを
化学品製造メーカーである同社では従業員の多くが製造業務に従事している。従業員の4割は工場勤務であるが、高齢期に体力負荷軽減のために事務部門への配置転換も想定された。 そこで異動後に不可欠となるパソコン基本操作の獲得を目的に研修が計画され、それまでパソコンとあまり縁のなかった現場作業の高齢者も問題なく、報告書を作成できるスキルを身に付けている。
高齢者がパソコンを使いこなせれば日常の報告や届出が円滑に行なえるだけではなく、自身の技術や知識を自身で電子化できるようになる。データ化のため手書き文書をOCR(読み取り装置)にかけても読み取れないこともある。手書きではなく最初からデータで作成して残せれば社内データベースからの情報検索が容易となることから、業務の効率化にも繋がっている。
■無理なく働ける勤務形態を用意
各職場では高齢者に重労働をさせない配慮がなされている。全役職員対象の面談や日々の上司への相談事項、自己申告された健康状態も考慮し、配置転換が行なわれることもある。多様な働き方を用意し、テレワーク制度は2020(令和2)年に導入、仕事と介護の両立、高齢者や障害者の就労促進、非常災害対応を目的とし、導入されている。現在の利用者は育児中の社員であり、高齢者の利用はない。
健康管理・安全衛生・福利厚生
■作業環境の改善
休憩所を見直し、畳で横になれる部屋を用意した。安全衛生委員会で安全管理者と衛生管理者が連携して熱中症対策に取り組み、職場では塩飴を支給、高温となる作業場では手もとで温度調節できるエアラインスーツを着用して作業にあたる。
■健康管理の啓発
1か月に1回(2日間)の健康管理デーを設けて血圧・体重測定を実施、健康維持を啓発している。喫煙者を対象に禁煙奨励金を支給している。定期健康診断後に要再検査となった者には産業医が再検査を促している。
■表彰制度
永年勤続表彰は勤続10年以上の者を対象に5年ごとに行なっている。高齢者からは「表彰されて身が引き締まる。これからも頑張る」との感想が聞かれる。
■懇親会の開催
役員主催の懇親会が行なわれ、同じ会社の従業員でありながら日常は接点のない部門や年齢層の間での交流が促進され、部門間協力の基礎となる。
制度改定の効果と今後の課題
定年延長により総人件費は増えるが、若手社員がベテラン社員から指導を受ける機会も増えるので人材確保の視点から総合的にはプラス効果と判断している。 なお、60歳から70歳へと定年年齢を一挙に10年引き上げた同社は常に現状を見直しており、労働力充足と若手人材育成を担う高齢者が今後も働き続けることを可能とする新たなスキルを身につけさせ、また、ベテランの高い意欲が維持できる制度の構築に努めている。

