-高齢者のみならず皆にやさしい設備や機器の導入で働きやすさ向上-
山田工業株式会社
- 70歳以上まで働ける企業
- 人事管理制度の改善
- 賃金評価制度の改善
- 戦力化の工夫
- コンテスト入賞企業
- 上限年齢なしの継続雇用(基準あり)
- 技能伝承
- 多様な勤務形態
- 作業環境改善

企業プロフィール
-
創業昭和13年(1938年)
-
本社所在地富山県富山市
-
業種金属製品製造業
-
事業所数2か所
導入ポイント
- 改定の契機:装置製作と若手育成に不可欠な熟練高齢者の長期的活用
- 長い年月をかけねば育成不可能な熟練技能者を長く活用するため70歳までの再雇用を制度化
- 高齢者の負担軽減を考えた勤務形態を用意、短日数勤務や短時間勤務が選択可能
- 行政サービスを利用して外部出身者採用を強化、適材適所で各部門に配置
- 改定の効果:「安心して働き続けられる」、「将来の不安がなくなった」と高齢者が評価
-
従業員の状況従業員数 63人(2023(令和5)年6月現在) / 平均年齢 47.8歳 / 60 歳以上の割合 33.3%(21人) 60~64歳 4人/65~69歳 9人/70歳~ 8人
-
定年制度定年年齢 60歳
-
70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 ・希望者全員 ・ 70歳以降は基準該当者を上限年 齢なく雇用
同社における関連情報
企業概要
山田工業は1938(昭和13)年創業、現在は化学プラントや環境プラントに設置される圧力容器や熱交換器等を製造し、製品は国内だけではなく海外にも輸出されて現地の工場に据え付けられる。製造する機材は発注企業や設置場所で様や材質が異なる。同社は設計から製作、現地据え付けまで全工程を担当、製作では鉄やステンレス等多様な素材を溶接・製缶する技術力の高さが評価されている。同社が手がけた製品は工場だけではなく公共施設にも設置され、多くの人々目にする。鉄板やパイプなどの素材が複雑な形状に加工され最終製品として送り出される時、製作担当者は感慨深い気持ちになるという。
従業員は63名(正規36名、非正規27名)、年齢構成は60歳未満42名、60?64歳4名、
65~69歳9名、70歳以上が8名、平均年齢は47.8歳である。現在、最高齢者は79歳である。

雇用制度改定の背景
■現有人材で人材確保
同社の定年は60歳、その後は65歳まで希望者全員を再雇用していたが、2021(令和3)年に希望者全員70歳まで再雇用と改めた。人手不足が続き新規採用が難しい状況下、現在働いている従業員により長く働いてもらうことが必要となっていた。 長く働き続けたいと考える高齢者も多かったことから人事部門で検討を進め、継続雇用の上限年齢引き上げを経営陣に提案、承認され実施となった。
■熟練技能を持った人材の長期的活用
同社の技術力を担える現場作業者は一人前になるまでに10年程度を必要とし、短期間で育成できるものではない。これら熟練技能者の長年にわたる貢献が同社を支えてきた。一方、現在では高齢化が進み、全従業員の約3分の1が60歳以上に、4分の1が65歳以上となっている。現在在籍しているベテランがより長く働ける制度を整備し、安心して蓄積された能力・知識を発揮してもらえるようにとの考えから継続雇用期間を65歳から70歳まで延長することとなった。
人事管理制度の概要
■人材育成
技術力を強みとする同社は採用者を入社後3か月間、県立の技術専門学校金属加工科の短期課程で学ばせる。社員の多能工化を目指し、事務職採用者も受講させている。
■賃金制度と評価制度
賃金は年齢給と職能給からなり、年齢給は60歳近くまで昇給がある。 業務に必要な資格保有者には資格手当が支給される。目標管理シートによる人事考課は正社員のみが対象である。
■役職定年制度
役職は事務職が部長、課長、係長、主任、製造職がグループリーダー、サブリーダーからなる。 運用上、役職定年は60歳で主任と係長は離脱するが、部長と課長の場合は後継者が育っていない場合は引き続き役職を担うことがある。
■継続雇用制度
定年が近づくと管理職と面談し、再雇用希望の有無、再雇用となった場合の働き方について話し合う。 再雇用者の賃金は60歳定年時の80パーセント程度である。再雇用後も人事考課で評価され、評価が高く定年前と遜色ない賃金を得る高齢者もおり、その意欲は高い。
なお、70歳以降の継続雇用実績もあり、本人の希望や適性、会社の評価を総合的に勘案し、6か月更新で再雇用している。 上限年齢はないが本人の健康状態が最も重視される。
■外部人材の採用
高齢者の新規採用も行なっている。富山くらし・しごと支援センター、とやまシニア専門人材バンクを活用している。同社では他社経験のある60歳以上のUターン人材をこれまで6名採用、その経験を活かせる職務に配置しており、ISO認証取得業務、測定器具管理担当の管理職として登用している。外部出身者からは内部人材が気づかない改善提案がなされ、貴重な人材となっている。
高齢従業員戦力化のための工夫
■強みを活かして後進育成
若手人材の技術力高度化を課題ととらえ、高齢者とのペア就労でOJTによる技能伝承を溶接・製缶・旋盤の各班で推進している。同社では全社員のスキルマップが整備されており、若手についても一人ひとりの育成課題を把握している。会社主導で「今回はこのテーマを習得させる」と決め、高齢者を指名して任務にあたらせる。同社が受注する製品は毎回仕様が異なり、それまでの知識や経験が通じにくい部分もある。マニュアルでは伝えきれないノウハウを高齢者が若手に指導している。

■無理なく働ける勤務形態を用意
高齢者の体力に応じた勤務形態を用意し、短日数勤務(現在、2名が週3日勤務)や短時間勤務を選択できる。三世代家族の高齢者は制度を利用して朝ゆっくり家事をしてから出勤し、早い時間に帰宅して孫の世話をしている。「無理なく働けて自分の時間が十分持てる」と評価している。また、同社の役員を引退後、週3日、1日7時間勤務で若手を育成している高齢者は重責から離れ、意欲的に後進を指導している。
■若手の協力で高齢者もITに対応
全社で職場のIT化を推進しており、2020(令和2)年のグループウエア導入で情報が共有できるようになった。ペーパーレス化を進めるためタブレットを導入、作業日報と社内連絡が閲覧でき、勤怠管理や業務の進捗管理も容易になった。タブレットで残業届も提出できるが、高齢者のなかには操作が難しいと感じる者もいる。そこで入力方式を文字入力ではなくペン操作で可能にしている。現場では若手が操作方法を高齢者に教えることも多く、両者間でのコミュニケーションも深まっている。
■外国人技能実習生のよき相談相手
同社で働く外国人技能実習生の指導や生活上の相談に乗っているのは高齢者であり、長年にわたって培ってきた技術や技能を教えるだけではなく、日本で生活するうえでの注意点、人生経験からのアドバイスなど多岐にわたる支援を行なっている。
健康管理・安全衛生・福利厚生
■高温作業の改善
現場作業では夏場でも溶接作業があり、40度を超える高温作業となる。スポットクーラーだけでは不十分なため空調服を支給、作業時の疲労軽減に努めている。また場内には給茶機とスポーツドリンクを常置し、熱中症予防に努めている。
■ターニングロール導入で溶接作業を改善
曲げた鉄板を溶接して作るタンクは重量物のため作業場に置いた状態で製作、作業者は時には体をかがめ、無理な姿勢で4方向(下向き、横向き、縦向き、上向き)から溶接し、疲労につながっていた。品質を高めるには下向きから溶接するのが最も望ましい。そこで溶接姿勢の改善を目的にターニングロールを導入、作業者は加工物をロール上で動かすことで常に下向きで溶接でき、無理な姿勢で作業することがなくなった。

■作業中に疲れたらその場で休める配慮
加工作業では工作機械が使われる。コンピュータ制御ではない汎用工作機械は熟練した高齢者が操作する。汎用旋盤の横にパイプ椅子が置かれており、作業する高齢者は疲れを感じた時にいつでも座って休むことができる。疲労防止となるほか、足腰への負担も軽減された。
■重い扉を電動化
工場入口の両開き扉は重く、二人がかりで開ける力仕事であった。この扉を電動化したことにより体力負担なしに一人で容易に開けられるようになった。
■高齢者に負担をかけないルール
高齢者の疲労防止を目的に若手と高齢者で役割を分担している。重量物の運搬や分厚い鉄板の歪みをハンマーで叩いて矯正するなどの力仕事は若手が担うことを職場のルールとしている。また、同社では製品据え付けのための出張も多いが、65歳を超える高齢者には負担軽減のため県外出張はさせていない。
■文字が見やすい大型ディスプレイを設置
現場やオフィスで使用されるパソコンディスプレイを17インチから24インチに拡大した。これにより文字が大きく見やすくなっただけではなく、画面スクロールの必要も少なくなって効率が向上した。
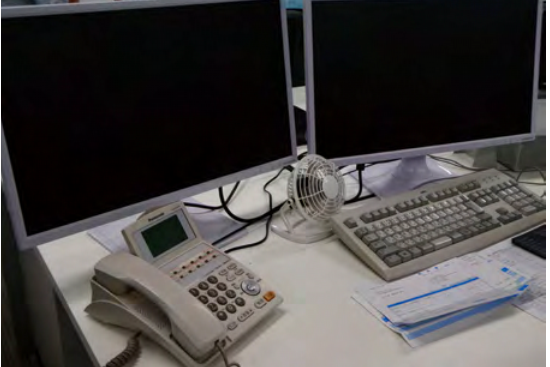
■工場内の照明をLED化
工場内の照明は白熱灯や水銀灯からLEDへ更新して照度を向上、照明のチラつきがなく目の負担を軽減したほか、点灯時間が短くなって作業にすぐ取りかかれるようになった。
■楽な姿勢で使えるシャワー室を設置
溶接作業では作業者に金属粉が付着するため手洗い場で洗い落とす。これまでは洗い場で地面に座って洗い落としていた。現在は流し台を導入、楽な姿勢で洗えるようになった。
また、帰宅時にシャワーを浴びて身体をきれいにしていたが、温度調整が難しいボイラー利用の熱湯利用から温度調節できる温水シャワーへ改善、快適になった。
■職場単位で作業と危険箇所をチェック
ラジオ体操後に各グループでミーティングを行なって危険箇所を確認している。また、日常から管理監督職が声かけを行なって各人の様子を確認、その日の作業内容をチェックし、高齢者に負担がかかりそうな作業は若手に振り替えている。
■高齢者向けの健康診断メニューの充実
定期健康診断の検査項目では高齢者用にがんや内臓検査に関するものを追加している。また、高齢者と産業医の間で定期的に健康相談会を開催、産業医を通じて定期検診後の2次検診受診を促している。
制度改定の効果と今後の課題
現在の取り組みは効果を上げており、社員からは「安心して働き続けられる」、「将来の不安がなくなった」と好評である。将来的には希望者全員75歳までの継続雇用も構想しており、その実現には勤務形態の再検討が特に重要であるとしている。
