株式会社上野村きのこセンター
-山村で高齢者に雇用の場を提供、定住促進と産業振興に貢献-
- 70歳以上まで働ける企業
- 人事管理制度の改善
- 賃金評価制度の改善
- 戦力化の工夫
- コンテスト入賞企業
- 75歳までの継続雇用
- 配置や勤務時間に配慮
- 健康管理
- 作業環境改善
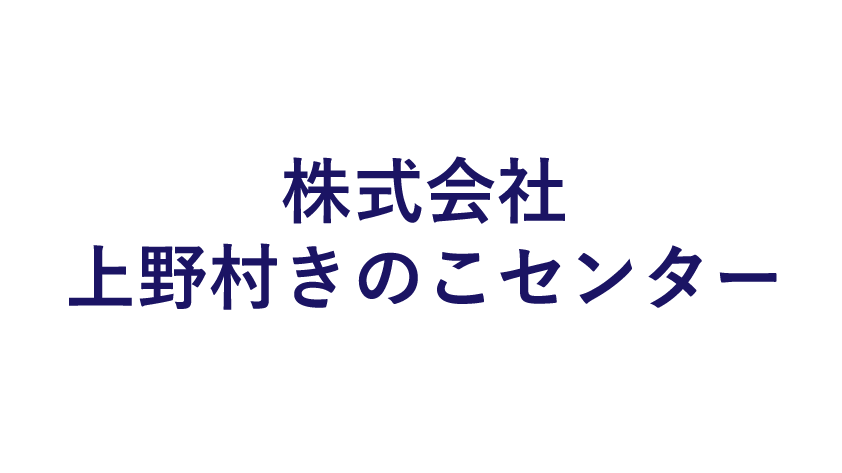
企業プロフィール
-
創業平成27年(2015年)
-
本社所在地群馬県多野郡上野村
-
業種農業(菌床しいたけの製造・しいたけ加工販売)
-
事業所数1か所
導入ポイント
- 改定の契機:高齢者が長期にわたって仕事の知識や経験を活かせる会社の実現に向け制度改定
- 定年を60歳から65歳へ、継続雇用上限年齢は希望者全員75歳まで延長
- 運搬作業改善など高齢期も負担感なく仕事を続けられる「重いがない職場つくり」を実践
- 会社の利益還元の一環として入院時の医療費個人負担分も会社が負担、高齢者の健康を維持
- 改定の効果:75歳までの雇用機会保障により高齢者はもちろん中堅従業員の安心感も向上
-
従業員の状況従業員数 51人 (2023(令和5)年6月現在) / 平均年齢 49.3歳 / 60 歳以上の割合 37.3%(19人) 60~64歳 4人/65~69歳 6人/70歳~ 9人
-
定年制度定年年齢 65歳 / 役職定年 なし
-
70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 ・希望者全員 ・ 75歳以降は基準該当者を上限年 齢なく雇用
同社における関連情報
企業概要
株式会社上野村きのこセンターはしいたけの栽培、加工、販売を行なう企業である。同社が立地する群馬県上野村は人口約1000人の小規模自治体であるが、村による住居斡旋、生活費補助、育児支援、医療支援等の定住支援策が充実しており、村民の約2割は「自然のなかで暮らしたい、働きたい、子育てがしたい」と考えて同村に移り住んだUターン者やIターン者である。同社も村による産業振興や雇用促進の一環として2000(平成12)年に村営きのこセンターとして誕生その後、2015(平成27)年に株式会社上野村きのこセンターとして株式会社化(社長は上野村村長が兼任)、現在は上野村最大の雇用の場となっている。2016(平成28)年には新生産ラインでの本格出荷を開始、また、2017(平成29)年には廃菌床のバイオマス燃料化事業を開始、業容を拡大している。
同社は行政とは違った視点、企業ならではの強みで村の振興を担っている。自社の業績を向上させ、村で生まれた人や帰ってきた人が働ける場、働きに見合った給料をもらえる場としての地位を確立している。 村が設立した同社は黒字企業として村に貢献している。また、同社が中心となって村内の企業と連携し、お互いの強みを活かした協業など地域振興を推進している。

従業員は51名、うち10名が正社員、41名がパートである。正社員は管理部門、パート社員は現場作業を担っている。年齢構成は60歳未満32名、60歳代前半4名、同後半6名、70歳以上9名、平均年齢は49.3歳である。
雇用制度改定の背景
同社は2022(令和4)年3月、定年を60歳から65歳へ延長した。定年に達した日の属する月の末日が退職日である。再雇用の上限年齢も見直し、希望者全員を対象にそれまでの65歳から75歳へ延長、雇用機会を提供している。なお、パート社員の定年は75歳である。
同社では従来から他社で定年退職した高齢者をパート社員として受け入れており、定年後も働きたい人々の受け皿企業となっていた。60歳代後半になって能力が落ちる例もなく、より長期に雇用機会を提供することに問題はなかった。高齢者が仕事の知識や経験を長期間活かせ、働き続けたいと思える会社を目指していたことから定年延長と再雇用上限年齢の引き上げを実施した。なお、正社員の数が少なく若手も多かったことから、これまで正社員で定年を迎えた者はいない。
定年延長の効果はすでに現われている。同社では前職で経理の経験がある定年退職者を経理業務で起用したが、60歳定年制だったためパート社員としての処遇となっていた。65歳定年制移行により正社員としての登用が実現、仕事に見合った処遇を提供できるようになり、実力発揮の環境も整った。
人事管理制度の概要
■採用
同社の正社員は管理業務を担っている。正社員は不足しており、新卒もしくは中途採用で年1名程度採用している。きのこに興味を持ち、きのこ栽培の仕事が好きで、高齢者と働ける礼儀と協調性のある人を求めている。入社後のギャップ軽減を目的に職場見学を実施しており、仕事内容と企業風土を理解したうえでの入社となる。村に戻って同社の採用に応募する人々の志向はさまざまであり、パート希望者もあれば正社員希望者もいる。
■賃金制度と評価制度
同社の賃金は基本給、業績給、扶養手当、役職手当からなる。人事考課は出勤率と能力評価で行ない、部長と社長(村長)で確認、年1回の昇給と賞与に反映される。業績を上げている者は職位が上昇し、職位に応じて基本給に係数を掛けて賃金が決まるため、これが業績給となる。 かつては役場職員同様に差をつけない横並びの賃金決定方式であったが、現在は職務遂行実績の違いを反映した賃金制度に移行中である。評価結果は最低でも年1回行なわれる個人面談でフィードバックしている。
なお、退職金は中小企業退職金共済事業本部(中退共)に加入している。
■継続雇用制度
就業規則に「定年後75歳まで継続雇用する」と明記している。定年後も引き続き勤務を希望する者は定年予定日の6か月前までに会社に申し出る。正社員から嘱託従業員に変わり、雇用期間は1年更新となる。 定年後の賃金は定年前の賃金を時間給に換算して計算する。 継続雇用者も人事考課の対象であり、考課結果は時給の昇給に反映される。なお、本人が希望し会社が認めた者は75歳以降も年齢上限なく再雇用される。この場合も1年更新であり、引き続き勤務を希望する場合は、嘱託期間満了日の6か月前までに会社に申し出る。
高齢従業員戦力化のための工夫
■高齢パート社員の仕事
しいたけ栽培は熟練作業者を必要とする。しいたけの栽培は100日程度かかり、その間、さまざまな面で人の手を必要とする。培養は室温22度、湿度70パーセントの培養室に置かれた菌床で始まる。菌床はおがくず等の成分を調整して作る。培養で白くなった菌床がさらに黒色へ変化すると、きのこを発生させる部屋に移す。この部屋は昼間18度、夜間13度で変温管理している。しいたけ栽培は一日の温度差がポイントとなる。
このようにして大きく肉厚なしいたけが育つが、日々の成長度合いは人の目でチェックされる。作業者はいちばん美味しい時期を迎えたしいたけを見逃さず、菌床のなかから瞬間の判断で良品を選んで採り分ける。収穫されたしいたけは包装、出荷される。同社は乾燥しいたけも製造している。パート社員は機器類のメンテナンス、廃菌床を利用した燃料の製造も担う。
■希望する仕事への配置
同社で働く高齢パート社員のほとんどが地元出身である。女性パート社員は主婦が大半であるが、男性パート社員の前歴は製造業、林業、消防士、塾講師、役場職員、役者、税務署職員と多彩である。 最高齢者は74歳の男性で、しいたけの栽培、間引き、収穫を担当している。
パート社員は働く理由も収入確保や健康維持など多様である。また、責任のない仕事に就きたい者もいれば、補助業務ではなく「現役」として期待され、定年前と同様に責任を与えられての仕事を望む者もいる。同社では高齢者の意向を聴いて担当職務を決定、その後は同じ仕事を続けてもらうことで安心感を与えている。
■3K作業の解消
農業が3K(きつい、汚い、危険)労働または3Kプラス「休めない」とイメージされ、敬遠されることがあるが、同社はその対極(軽作業、汚れない、危険作業なし)を実践している。しいたけ栽培や収穫はハウスの中で行なわれ屋外作業はない。また仕事は毎日変わらず、作業量は平準化されており、高齢者が多いパート社員に過重な負荷がかからないようにしている。
■体力負担の軽減
同社が目指すのは年を重ねても続けられる「重い」がない職場つくりである。 配送業務でも「重い」作業を解消した。これまで配送ドライバーは毎朝パレットにしいたけの入った箱を300 ~ 500個手積みして出荷していたが、自身が60歳なった時には体力が続かないと危惧していた。
そこで配送用の冷蔵庫を設置、前日に他の従業員が冷蔵庫内のパレットに箱を積み込んでおくようにした。ドライバーは出荷当日にフォークリフトでトラックにパレットを載せるだけで済み、体力負担軽減と作業時間短縮が実現した。ドライバーはこの仕事を70歳まで続けられると考えている。なお、節約された時間はしいたけ生産に充てることもでき、売上高向上と従業員収入のアップにもつながった。

■作業環境の改善
同社のしいたけ栽培は屋内作業ではあるが、夏の猛暑、山間部の冬の底冷えの影響は屋内にも及ぶ。そこで作業場の冷暖房を増設、特に高温下での作業負担軽減につなげている。
■働きやすい勤務形態
パート社員の要望に応え、多様な勤務形態を設定している。 短日数勤務(月8・10・14・15・16日のフルタイム)、短時間勤務(1日4・5・6・7時間)を用意している。
■高齢者の要望を反映した改善
現場の高齢者からの業務改善提案は少ないが、経営者は日常から現場を回るほか、毎日の朝礼で、パート社員を含む全員を集めて会議を開き、要望を聴き取っている。その結果、フラットな作業台や重量物運搬用の車輪付き台車が導入された。
■高齢者の経験の伝承
パート社員の作業はチームではなく個人で行なわれる。 勤続年数の長い高齢者が未経験者を直接指導することはないが、高齢者の仕事の進め方や作業で注意していること、仕事に対する向き合い方が他者の参考になる。50歳代より60歳代、70歳代高齢者の作業スピードが速いこともある。ともに仕事をする若手が何かを感じ取ることで技能が伝承される効果が期待できる。
■外国人技能実習生の指導
同社では外国人技能実習生を毎年2、3名採用しており、高齢者が指導役である。高齢者は作業に関することだけではなく日本での生活についてアドバイスしている。
健康管理・安全衛生・福利厚生
■会社が入院時の医療費を全額負担
同社は会社利益の従業員への還元として、入院時の医療費の個人負担分も会社払いとしている。高齢者の多いパート社員は健康上の問題が起こる可能性も高くなるが、会社が全額負担してくれるという安心感を与えている。
■イラストによる注意喚起
イラストを作業場の各所に掲示し、労働災害防止を注意喚起している。体に負担のない姿勢を文章ではなくイラストで示すことで直感的に訴えている。

制度改定の効果と今後の課題
75歳まで働ける制度により従業員の安心感が高まった。子どもの独立が高齢期に重なる社員にとっては定年延長と75歳までの再雇用が安心感を与えている。 一方、現在64歳の正社員がこれから継続雇用に移行する。正社員から継続雇用する初めてのケースであり、体力や職務遂行能力の変化を注視し、要望があれば制度改善を検討する方針である。
