株式会社 横引(よこびき)シャッター
-企業理念「社員は家族」に基づくマネジメントと社員に寄り添う職場づくり-
- 70歳以上まで働ける企業
- 人事管理制度の改善
- 賃金評価制度の改善
- 戦力化の工夫
- 能力開発制度の改善
- コンテスト入賞企業
- 上限年齢なしの継続雇用<運用>
- 技能習得等による昇給システム
- 多能工化推進による柔軟な勤務形態
- 作業環境改善

企業プロフィール
-
創業1986(昭和61)年
-
本社所在地東京都足立区
-
業種その他の製造業
-
事業所数4か所
導入ポイント
- 改定の契機:技術を教えると居場所を失うという高齢社員の不安解消と円滑な技能継承
- 技術習得による昇給や技能継承を手当に反映するなどの取組により意欲・能力を向上
- 定期的な担当部署入れ替えで多能工を育成するフォロー体制で柔軟な配置を実現
- 通常業務を行わない日を設定するなどして3S活動を推進
- 改定の効果:高齢社員の長期活躍期間の確保により余裕をもった事業計画の策定を実現
-
従業員の状況従業員数 35人(2023年6月現在) / 平均年齢 60歳以上 16人 (内訳)60~64歳 3人、 65~69歳3人、 70歳以上10人 / 60 歳以上の割合 45.7%(16人)
-
定年制度定年年齢 70歳 / 役職定年 なし
-
70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 定年70歳。運用により希望者全員を年齢の上限なく再雇用
同社における関連情報
企業概要

株式会社横引シャッターは、1986(昭和61)年にグループ会社である株式会社中央シャッターのもとに、東京都足立区綾瀬に創業した。創業以来、「お客様」、「社会(世の中)」、「会社(社員)」が豊かで幸せになれる「三方よしの精心」を経営の柱とし、各種シャッターの全製品をオーダーメイドで設計・製造・施工し、その販売までをトータルで行っている。
また、新発想で考案した「横に引いて開閉する上吊式の横引きシャッター(特許取得済み)」は国内トップシェアを占め、その使い勝手と防犯性が評価され、駅ビル・ショッピングモール・病院などに広く普及しているほか、個人宅のガレージ用としても人気が高い。また、自然災害に強い防火型シャッターを製品開発するなど、顧客の様々な要望をカタチにし、より満足度の高い製品を提供している。その卓越した技術力と斬新な発想による製品化・業績が評価され、2008(平成20)年には「足立ブランド認定企業」に認定された。

雇用制度改定の背景
■経緯
社員35人のうち、60歳以上が16人で、全体の45. 7%を占めている。2022(令和4)年2月までは、94歳の社員が現役で活躍していた。現在の最高齢者は81歳で、設計業務を担当している。
特許による独自型シャッターのため製作・設置の経験者は外部から採用できず、かつ繊細な感覚が要求される作業はマニュアル化が難しく、経験豊富な高齢社員の技能が頼りとなるため、その人材確保が課題となっていた。また、後任や代理を入れると「会社はもう自分を必要としていない」、「技術を教えたら自分の居場所がなくなってしまう」という不安から表面的な技術承継が多く、ベテランの高齢社員が退社するとその技術を一から積み上げなければならいないという問題があった。
二代目の現社長は、創業者が掲げた「社員は家族」という経営理念に基づき、それを見えるかたちで実現すべく様々な取り組みに着手している。
人事管理制度の概要
■運用を明文化し技術と人材を確保
改定前までは、定年60歳、希望者全員65歳まで正社員として継続雇用、その後も運用により希望者全員を年齢上限なく正社員として継続雇用していたが、運用では雇用延長の適用になるか不安との声があった。 そこで、定年到達者については、①技術・能率について加齢による目立った衰えが見えないこと、②特許を取得している独自型シャッター(オーダーメイドを含む)の製作・設置には卓越した技術が必要であること、③上記②の技術に関する若手への技術のスムーズな継承は必須であること、などを踏まえ、今後の会社の未来を見据えて、2021(令和3)年9月に定年を70歳まで引き上げた。なお、70歳以降についても運用により希望者全員、年齢上限なく正社員として継続雇用している。
■技術習得や技能継承による処遇
給与体系は、5つの職種(営業、設計、製品製造、工事作業員、事務職)の採用時の基本給に加え、役付手当、職務手当、技能習得や評価結果(能力評価、業績評価、会社に対する貢献度評価で構成)などを反映した技能手当などで構成されており、現在の最高年齢の81歳の社員も80代で昇給しているが、これは技術の習得や経験を積むことで随時昇給していくシステムによるものである。 賞与や退職金はないが、その分を考慮した月額給与を支払っている。
また、定年前後の年齢による処遇の変化はない。ただし、特許によるオリジナルなシャッターを製造するにはその技術が欠かせないため、定年後の給料を下げない一つの条件として、若い人への技術の承継をあげている。定年を迎えた社員を継続雇用する際には「若手社員へ技術を教えてほしい」と要望を伝え、目標とした技能継承が実現すれば、手当や昇給に反映させる仕組みを導入し、技能継承の機会を担保した。これにより、技術を伝授することで自身の存在価値を失うことを危惧していた高齢社員による技能継承がスムーズに行われるようになった。
高齢従業員戦力化のための工夫
■柔軟な勤務形態等によるサポート
定年後の社員については、本人が働きやすく負担とならないよう勤務日は週2?6日の選択制とし、出退社時間もフレックス制としている。通院や家庭の事情、雨天時の通勤負担を考慮した出勤日の振替調整や育児などの事情に合わせた在宅勤務への切り替えも可能としている。
また、加齢により自転車通勤ができなくなった高齢社員に対しては、会社負担での送迎を実施している。
■多能工化を推進して業務負担を平準
社員はメインとなる職種のほか、4か月に一度のペースで担当部署を入れ替えて社員の多能工化を実施している。営業と設計、製造と工事、事務と営業など日常的に異なる職種の経験を積んでいるため、繁忙期の人手確保や勤務調整の際に、人手が足りない部署への応援に対応することが可能である。
■ペア就労・技能継承
採用時は各部門の様々な分野に関わり、そこで高齢社員による基礎技術などの指導を受けることで、本人ができる分野を見つけていくフォロー体制を実施している。 技能継承に関しては、高齢社員と若手社員が二人一組で高度な技術を必要とする作業を実施している。社長が社員との日々のコミュニケーションで技能継承が上手くいっているか確認し、不安や心配ごとがあれば払拭できるようにフォローしている。
高齢社員の多くがお金よりも働く居場所と生きがいを必要としており、自身の手当や昇給だけでなく、「若手社員の成長」にやりがいや大きな喜びを特に感じている。結果、年齢に関わらず、知っている人が知らない人に当たり前のように術を教える風土が出来上がった。
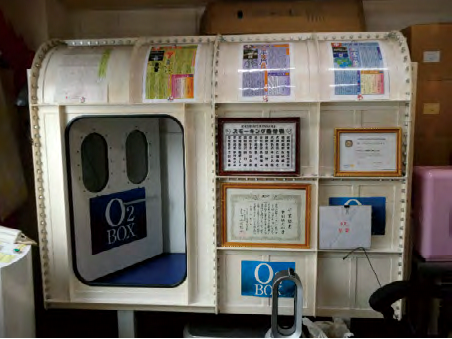
■知識・技術の向上
本人の希望があれば、業務に必要なスキル向上や習得のための研修を会社負担で受講できる。高齢社員向けのパソコン教室の受講や現場に必要な各種資格取得が可能なため、社員の満足度は高い。
健康管理・安全衛生・福利厚生
■身体的負担の軽減
高齢社員が着席状態で概ねすべての作業ができるように、着席時の視点に合わせて機械や作業台を設置している。若手社員には、立ち作業や高いところのものを取ってもらうなど役割を分担。荷物運搬用のフォークリフトを導入し、工場内にエレベーターを設置している。また、デスクワーク作業の設計・事務担当者向けに対しては、長時間座っても負担のない椅子に変更し、ゲルクッションも配付している。
■ITツールの活用
作業時の設計書などの確認の際は、タブレット端末を使用している。データ化による作業スペースの確保や整理整頓、画面の拡大縮小ができるため、作業効率が向上した。操作方法が容易なため文字やイラストをすぐ表示して説明することができ、若手育成の際にも重宝している。また、社内連絡は、携帯電話で行い、離れた作業場でも常に情報共有することができる。
■健康管理
熱中症対策として、作業場の各所に室温表記付きのデジタル時計を設置し、クーラーや扇風機、シャッター開閉による定期的な換気を行って室温調整している。また、水分補給のために、工場内に冷蔵庫や自販機を設置している。休憩室には塩タブレットを常備しているが、その消費状態により、社員の健康状態や作業環境の状況を確認している。
その他、定期的な通院が必要な社員には、病院が比較的空いている平日を活用できるよう有給休暇の取得の推奨や勤務形態の調整を行っている。また、全社員が利用できる酸素カプセルの導入、作業場の全面禁煙(分煙室を分離)などを実施している。
■安全衛生
転倒・落下防止のため、段差はスロープへ変更し、階段には分かりやすいように赤色の手すりを設置している。耐震対策として、棚には保管物の落下防止バーを設置している。作業場や機械には、巻き込み防止のための「手
袋禁止」や「メガネ着用」などの危険防止ステッカーが貼られており、誰もが分かるように英語やイラスト表記を併用し、ケガや事故を予防している。
また、駐車場を改装して、社員専用の駐輪場スペースを確保した。駐輪場の床は、滑り止め剤を通常の1. 5倍配合した素材で塗装しており、より滑らないように工夫している。
■「通常業務をしない日」を設定し業務改善
工場長の許可を得て、各自で出勤日に通常業務をしない日を設定し、その日は「私がキレイにし隊ビブス(ゼッケン)」を着用して共用部分の整理整頓をしたり、業務改善として改善前後の記録を報告したりしている。質
問の受け答え以外は通常業務に当たらないため、急遽人手が必要な場合は他の人が対応するなど多能工化の促進にも寄与している。

制度改定の効果と今後の課題
運用により65歳以上の雇用延長を行ってきたが、70歳までの定年を明文化することにより、高齢社員は勿論のこと若手の社員からも「この会社で長く働くことができる」という安心感が生まれ、全力で日々の業務に向かうことができている。また、高齢者雇用の環境整備を進めたことによる目に見えない効果として、「高齢になっても会社が守ってくれる」という信頼を得ることができた。「健康で真面目に一生懸命に仕事をしていれば、年齢は関係ない」との共通認識が社員に定着し、「技能継承しても、居場所はなくならない、むしろ評価される」とさらなる安心感をもたらしている。また、高齢社員が活躍できる年数を長く見込めることで、事業計画の策定に余裕を持てるようになった。
今後は、同時に若手採用にも力を入れ、社員が長く、楽しく働き続ける環境を継続して作っていきたいと同社は考えている。
