医療法人静和会浅井病院
-65歳定年以降も柔軟な働き方で高齢看護師が活躍-
- 70歳以上まで働ける企業
- 人事管理制度の改善
- 賃金評価制度の改善
- 65歳定年制
- 多様な勤務形態
- 看護師中途採用
- 高齢者と若手のシナジー
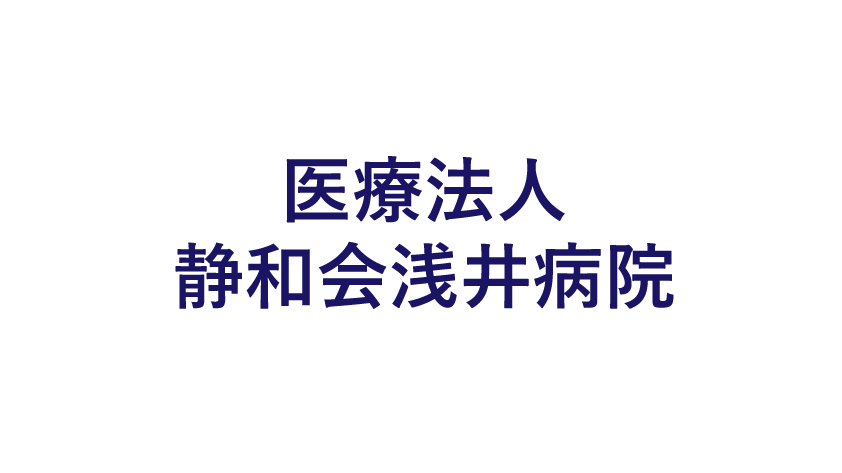
企業プロフィール
-
創業1959年
-
本社所在地千葉県東金市
-
業種医療業
-
事業所数3か所
導入ポイント
- 看護師の人材確保・人材不足の解消を目指し、65歳定年後の勤務延長
- 他病院で経験を積んだベテラン看護師の中途採用が増加
- 訪問看護分野で高齢者と若手のシナジー
-
従業員の状況従業員数 762名(うち看護職216名) / 平均年齢 45歳(看護職のみ) / 60 歳以上の割合 19.3%
-
定年制度定年年齢 65歳 / 役職定年 なし
-
70歳以上継続雇用制制度の有無 有 / 内容 勤務延長として上限なし
同社における関連情報
企業概要
■概況
医療法人静和会浅井病院は、1959年に東金市に開設した浅井医院を母体に同市で開業した。ベッド数447床(うち精神科360床)の、千葉県東部地区における精神科基幹病院である。精神科の他にも内科、消化器内科、整形外科、歯科などの診療科、人間ドックや認知症疾患医療センターも併設されており、地域の医療ニーズに対応している。精神科は、精神科救急施設にも指定され、デイケア、デイナイトケア、作業療法、訪問看護も行っている。また、同法人ではメンタルクリニック、介護老人保健施設(あさいケアセンター)を運営している。
職員数(2019月13日現在。非常勤含む)は762名で、最も多い職種は看護職で216名となっている。
■看護師の雇用状況
看護職は、病院に正看護師150名、准看護師45名、看護助手(ケアスタッフ)85名を配置し、あさいケアセンターでは正看護師20名、メンタルクリニックでは正看護師1名を配置している。精神科の特徴でもあるが、看護師の1/3は男性である。
看護師(正・准)の平均年齢は45歳で、60 ~ 65歳 が40名、65 ~ 70歳 が10名、70歳以上が6名になっており、60歳以上の看護師が約2.4割を占めている。看護師は、新しい技術を習得したいというキャリア志向もあって転職する者が多く、同病院も常時募集している状況である。しかしながら、複数の診療科を経験し様々な看護技術を習得した後、最終的に精神科を選ぶ者も多い。50代のベテラン看護師や若いころに同病院で働いていた者が、他の病院を定年退職してから戻ってくる例もある。
定年延長と勤務延長制度の見直し
■見直しの背景
同法人は、看護師の人材確保・人材不足の解消を目指し、定年の65歳以降は法人が必要と認める者(看護師等の有資格者)は年齢上限を定めず継続雇用することを就業規則で定めており、従来から長く働ける環境整備に取り組んできた。
しかしながら、継続雇用の条件として、65歳定年後は同じ部署内で勤務延長し、常勤(フルタイム)で働いてもらうことが前提であった。このため、家庭や自身の事情により勤務延長を希望せずに定年退職するケースが多い状況であった。こうした限定的な制度では「長く働ける」環境にならず、看護師等の人材確保が十分にできなかったことから、制度の見直しを図った。
■見直しの内容・効果
継続雇用の勤務形態は、常勤でのフルタイム勤務以外にも、非常勤の扱いになるが短時間勤務や週2、3日の勤務も可能となる。また現役時代と同じ部署に限らず、本人が希望する部署へ異動できるようにした。なお、勤務場所も病院内だけでなく、「あさいケアセンター」や別法人となる「ゆりの木苑」(特別養護老人ホーム)も選択できるようにした。65歳以降は、健康面での問題や個人の事情が様々になるため、本人が希望する働き方を柔軟に選択できる制度に変更した。
また、継続雇用の対象者は、有資格者(看護師、准看護師等)に限定していたが、職種を広げ、看護助手(ケアスタッフ)や施設管理(バスの送迎)といった者達も対象にした。
こうした見直しにより、病院の運営を支える多様な職種の人材が定年後も柔軟に長く働ける環境となり、スタッフのモチベーションの向上が図られたとともに、不足がちな看護職の人材不足が解消できた。
さらに、一度退職した者から再度働きたいという応募も多くなっており、本人の希望する働き方での再雇用に繋がっている。
人事管理制度
全従業員の賃金制度は、職種ごとの賃金テーブルになっており、年功と職能要素の色合いが濃い。前者は55歳で昇給が止まるが後者は65歳の定年まで昇給が続く。モチベーションの維持に寄与している面もあるが、賃金原資増に繋がっているため、年齢に関わらず役割や評価をベースにした制度への見直しを検討している。
定年後の賃金は、常勤で勤務する場合は、夜勤手当等の諸手当についても引き続き支給対象となる。
賞与は定年前後で変わらず年2回支給される。ただ、定年前は月給2か月分であるところ、定年後は1.5月分になる。非常勤となった場合は、職務に応じた時給制度になり賞与支給はない。
人事考課について、年間個人目標の設定と年2回の面談による達成状況の確認を行っているが、賃金には反映していない。若手職員のモチベーション向上や管理側と職員のコミュニケーション機会の増を目的として、賃金への反映を盛り込んだ新たな制度の導入を予定している。
高齢看護師へ期待する役割
■看護技術者としての期待
役職定年は設けていない。師長には主に4、50歳代の中堅の看護師が就いているが、全9名中2名は60歳代である。男性も3名いる。
看護師は患者と関わる仕事に専門性と生きがいを見出す者が多いため、師長への登用を希望しない場合が多い。師長の業務はマネジメントや看護業務の改善に取り組むことが中心となるが、こうした経験を若いうちから積むことは将来の看護業務に生きてくる。若いうちに師長としてのキャリアを経験させたいと考えており、役職定年を導入することの必要性も感じている。
一方で、高齢看護師には経験に裏打ちされた高い専門性を活かして活躍してもらいたいと考えている。
■夜勤の担い手
病棟には精神科で360床、内科で87床のベッドがあり、ほぼ満床の状況である。病棟勤務の看護師は、個々の事情への配慮はあるが、定年までは原則フルタイム勤務であり夜勤のシフトにも入っている。
夜勤は人員配置が少ない中で処置を行うため、一般的には、身体的にも精神的にも負担が大きいと敬遠される傾向にある。ただ、精神科病棟では夜間の緊急対応や処置が少ないこともあり、定年後の勤務延長者の中にも夜勤のシフトを希望する者も多く、年齢に関わりなく看護師が活躍している。
現在最高齢の看護師は、73歳(女性)の看護師、72歳(男性)のケアスタッフがいる。2名とも常勤であり、ケアスタッフは夜勤も担当している。
■訪問看護
同院では、精神科訪問看護(アウトリーチ)にも力をいれている。在宅生活を継続しながら治療を受けられるよう医療面・生活面の支援をチーム(看護師、ケースワーカー)で行っている。訪問看護では、患者の在宅生活を服薬管理や病状の変化や合併症の可能性なども視野にいれながら支えていく必要があり、専門知識や高いスキル、数々の症例を経験し得た対応力が求められる。経験の浅い若手の看護師よりもベテランの看護師の能力や経験が発揮できる場面が多く、定年後の看護師が主戦力となっている。
現在の最高齢の看護師は76歳だが、週1回程度訪問看護を担ってもらっている。訪問看護時の車の運転やパソコンの処理といった、高齢看護師が苦手とする作業が必要であるため、可能な限り若手看護師とペアにしている。そうすることで、高齢看護師は苦手分野をサポートしてもらえ、若手看護師は高齢看護師の処置や患者とのコミュニケーションの取り方などをすぐそばで勉強できる、といったシナジー効果が生まれている。
健康対策
同病院では、終業間際の救急搬送がない限り、ほとんど残業はない。
40歳以上の常勤職員は、自己負担なく人間ドックを受診できる。また、健康診断の結果、特定健診の対象となった職員は、同病院内の管理栄養士の指導を受けられるほか、所見があった場合は院内で精密検査を受けることができるなど、病院の特長を生かした対策を講じている。
今後の課題
現在の賃金制度には前述のとおりの課題が見られ、人事評価制度も導入が必要と認識している。同病院では、全職員の賃金・評価制度の抜本的な改善を図る予定。また、師長や主任等、役職を希望する看護師が少ないことから、管理職のノウハウを身に着けられるような「管理職研修」や「コーチング研修」の実施を検討中である。
さらに、入院患者の高齢化が進んでおり、介護色の強い看護業務が増えていること、看護師自体も高齢化していることも併せると、特に腰への負担が大きくなっている。現在は職員個人で補助ベルトを購入したり、病棟ごとに負担軽減の工夫を行ってきたが、病院全体としても対策強化が求められる。
| 内容 | 現状の課題 | 強化内容 |
|---|---|---|
| 賃金制度見直し |
年功序列要素が強く、 高齢職員増≒賃金原資増となっている。
|
各職員の役割や、 人事評価結果を反映することで、 年齢に依存しすぎない制度とする。 |
| 人事評価制度導入 |
目標設定と面談は実施していたが賃金等へ反映しておらず、 モチベーション向上に繋がらなかった。
|
賃金制度改善と併せて、 職員のモチベーション向上を図る。 併せて、 管理職と一般職員の交流機会を増やす。
|
| 身体的負担の軽減 | 看護師 ・ 患者双方の高齢化が進む中で重要課題だが、 自助努力が中心であり、 病院全体として取り組めていない。 | まずは病棟ごとに行っている工夫を共有し、良い取組は病院全体に広めていく。 |
| 若手と高齢者のペア就労 (実施済) |
訪問看護で高齢看護師のスキルが必要だが、 車の運転やPC作業が負担だった。 | 若手を同伴することで、 運転等のサポートを受けつつ、 技術伝承が行える。 |
